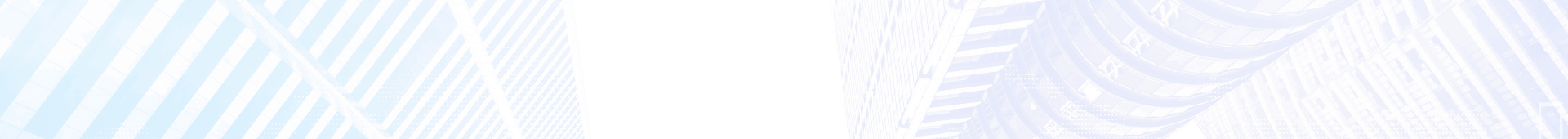

マーケティングでリードが獲得できていても、営業体制や商談プロセスが属人的でスケールしない、という課題は避けて通れないものです。
本記事では、SaaS営業を「モデル構築」「体制設計」「リード育成」「提案設計」の4フェーズに分けて解説します。営業戦略全体を俯瞰・再設計するガイドとしてご活用ください。
SaaS営業は、従来のように「契約して終わり」ではなく、継続課金・アップセル・CSを含む「ライフサイクル型営業」が基本です。営業担当は、導入前の課題整理から契約後の活用支援までを一貫して担います。とくに、BtoBでは複数の関係者が意思決定に関与するため、提案設計にも工夫が必要です。
こちらでは、SaaS営業の商習慣や営業スタイルの特徴を整理し、全体像を把握するために必要な基礎知識を解説します。
PMFを達成しても、営業体制が仕組み化されていなければ売上は頭打ちになります。多くのSaaS企業が直面するのが、属人性とプロセスの曖昧さによる再現性の欠如です。
以下の記事では、PMF達成後に必要な営業体制の考え方や各ポジションの役割、最小構成の組み立て方についてまとめています。詳細はこちらをご参照ください。
営業組織の再現性とスケーラビリティを高めるうえで、SDR(インバウンド対応)とBDR(アウトバウンド対応)の適切な分業は不可欠です。
以下の記事では、SaaSモデルに適切化されたSDR/BDRの役割定義・チーム設計・KPI設計・商談化プロセスを体系的に整理しています。「誰が・どのチャネルで・何を目的に接触するのか」の判断基準を明確にし、属人化しがちな営業活動を構造化するヒントを提供します。
「リードは取れているのに商談化しない」という課題は、SaaS企業でよく聞かれます。必要なのは、温度感に応じた設計と、接点づくりの仕組み化です。
こちらでは、セグメント別シナリオ構築やホワイトペーパー・ステップメールの活用、スコアリング設計とフォロー運用まで、再現性あるナーチャリング手法を紹介します。詳細は以下をご覧ください。
SaaS営業は単発の受注ではなく、継続利用による収益最大化を目的としたプロセスです。
リード獲得からカスタマーサクセスまでを分業体制で進め、効率性と再現性を高めます。契約後は定着支援やアップセルが重要で、顧客満足度を維持しながらLTV向上と解約防止を実現します。
SaaSビジネスの成功には、マーケティングと営業の連携が不可欠です。マーケティングが創出したリードを、営業が現場のフィードバックを基に質を高めることで、相乗効果が生まれます。連携不足は機会損失に直結するため、SLAの設定、定期的な情報共有、顧客情報の一元管理によって協力体制を築き、企業全体の収益向上を目指すことが重要です。
SaaS営業において、初回商談の成果を分けるのは「何を聞くか」よりも「どう引き出すか」。表層的な要望ではなく、業務構造や組織課題に踏み込むヒアリングが欠かせません。
ヒアリングは、提案論点を形成する設計フェーズと捉えましょう。現状の業務フロー、ボトルネック、評価指標など構造的な質問設計を行うことで、顧客自身が気づいていない課題を明らかにできます。また、関係者の意思決定構造や合意形成の流れも押さえることで、提案が止まるポイントを事前に見極めやすくなります。
提案フェーズでは、機能説明ではなく「顧客課題をどう解決するか」をロジカルに示すことが重要です。
提案書は、相手の意思決定プロセスと合致しているかどうかが鍵となるため、「現状整理→課題明示→解決アプローチ→提供価値→成果イメージ」という流れで進めるのが基本です。
また、工数削減率などの定量的な価値提示や導入ステップの明確化は、信頼感を高めます。同業他社の事例や具体的な活用イメージを示すことで、「この会社は自社を理解している」と感じてもらいやすくなります。
提案の精度が高くても、商談後の動きが設計されていなければ、検討は失速します。重要なのは、提案時点で「次に何をどう進めるか」を具体的に合意しておくことです。
商談は完結点ではなく、次の社内プロセスを動かす起点です。「○日までに社内レビュー」「次回は導入スケジュール調整」など、明確なアクションを共有することで、商談の宙吊りを防げます。複数の関係者が関与する場合は「誰がいつ登場するか」も想定し、社内稟議の停滞を防ぐ打ち手を用意しましょう。
実働だけではなく、営業プロセスの設計と仕組み化にも強みを持つ企業を厳選。単なる人手の投入ではなく、課題の根本からアプローチできるパートナー選びにお役立てください。


