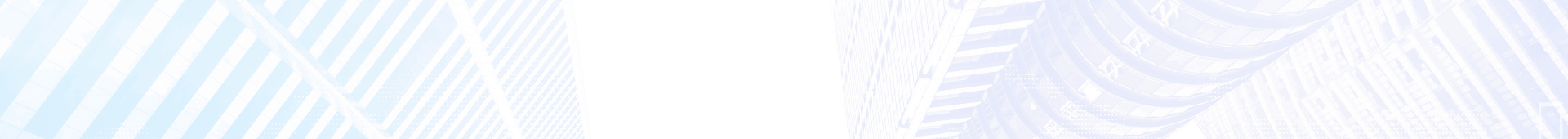

営業体制の強化を考えた際、大きく「内製営業」か「営業代行(アウトソーシング)」か、2つの選択肢が浮かびます。どちらを選ぶかによって、コストや社内ノウハウの蓄積量などが変わるため、慎重な判断が欠かせません。
本記事では、両者の違いを分かりやすく整理し、事業フェーズやリソース状況に応じた選択をするための視点を解説します。
営業体制を検討する際は、コスト構造・立ち上がりスピード・ノウハウ蓄積の3つの観点から比較するのが効果的です。以下では、それぞれの観点で内製と外注を詳細に見比べ、どちらが自社の優先事項を満たすのかを明確にしていきます。
内製営業では、まず人材の採用費や教育費が発生します。パソコンやツール類、営業資料の整備といった初期費用に加え、月々の人件費やオフィススペースのコストなど、固定費が重くのしかかる傾向にあります。
一方、営業代行は月額費用(あるいは成果報酬)にコストが集約され、固定費を変動費化できます。パフォーマンスが低ければ契約見直しで即コスト削減が可能なため、資金繰りリスクを抑えたいスタートアップや新規事業で採用しやすい手段です。
初期投資を抑えたいフェーズでは営業代行を活用し、長期的な運用を目指す場合に内製へ移行すると、費用対効果を大きくしやすくなります。
営業代行の費用相場を知りたい方は、ぜひ以下のコンテンツをご覧ください。
スピーディーな営業活動の開始を望むなら、営業代行に軍配が上がります。
内製営業は人材の採用から始まり、研修やチームビルディングなどの準備期間が必要となります。すぐに営業を始めることは難しく、短期で成果を求める場面では不向きです。
一方営業代行は、すでに営業のスキルや経験を持ったプロ人材が揃っているため、契約後に商材理解のキックオフを行った後、すぐにアクションを起こせます。特に新規事業やリード獲得が急務なフェーズでは大きな武器となるでしょう。
自社へのノウハウ蓄積という観点では、内製営業が優位と言えます。
自社の商材や顧客への理解を深めながらPDCAを回せるため、ナレッジやスキルが社内に蓄積されていきます。営業手法や改善策を自社仕様にカスタマイズしやすく、長期的な視点でみれば大きな資産になるでしょう。
一方、営業代行はノウハウが外部に蓄積されやすく、「委託を止める=成果も止まる」リスクがあります。トークスクリプトやナレッジ共有を行う会社も増えていますが、ナレッジの深度とタイムリーさとナレッジへの理解度の高さは内製に軍配が上がると言えるでしょう。自社の営業力を向上させるためには、最終的にノウハウを内製へ吸収できる仕組みづくりが鍵を握ります。
「内製か代行か」の二者択一ではなく、内製と外注の長所を同時に活かすハイブリッド型で運用する企業も存在します。以下では代表的な活用シーンを2つ取り上げます。
事業の立ち上げ当初は、営業代行でペルソナ・メッセージ・チャネルを高速で検証し、ヒットパターンを見つけ出します。その後、パフォーマンスが安定してきた領域から内製チームへ段階移行し、外注比率を下げていく方法です。
初期投資を抑えつつ市場ニーズを探れるうえ、育成すべき人材像や必要なツールが明確になるため、採用時のミスマッチを減らせます。代行終了後も、共有されたトークスクリプトやKPI設計を自社標準として活用できる点がメリットです。
外部リソースで事業拡大のスピードを担保しつつ、事業成熟に合わせて内製比率を高めることで、学習コストと機会損失の両方を抑えられます。
展示会やセミナー、Web問い合わせなどで獲得した見込み顧客は、製品理解が深い自社チームが対応して提案力を武器に商談化率を高めます。一方、まだ接点のないターゲット企業へのコールドコールや休眠リストの掘り起こしといったアウトバウンド活動は、営業代行に委託して手数とスピードを確保する方法です。
KPIは「内製=商談化率」「代行=アポイント数」と切り分けることで評価が明確になり、双方が自らの役割に集中できます。その結果、社内チームは顧客理解を深めつつ知見を蓄積でき、外部チームは短期間でリード数を増やせるため、両者の強みを生かした運用が可能になります。
営業代行を選定するうえで重要なのは、価格や実績だけではありません。
以下ページでは、自社に合うパートナーを見極めるための判断軸を詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
営業代行は、スピードや短期成果を重視するフェーズに適切であり、内製営業はノウハウ蓄積や自社資産の形成に有利です。それぞれに得意分野と課題があるため、自社の現状と目的に合った使い方が求められます。 例えば、事業立ち上げは営業代行を活用し、成果が出た段階で内製に切り替えるといった段階的な導入も選択肢の一つです。どちらかを選ぶのではなく、戦略的に使い分けることが成功の鍵になります。 営業代行サービスを検討する際は、内製との違いを把握した上で、事業のフェーズや課題に即した選択が大切です。
本サイトでは、営業戦略の設計から実働支援、リード育成やMA活用までをカバーする幅広い営業代行サービスをご紹介しています。自社に適した営業体制を構築するための一助として、ぜひご活用ください。
実働だけではなく、営業プロセスの設計と仕組み化にも強みを持つ企業を厳選。単なる人手の投入ではなく、課題の根本からアプローチできるパートナー選びにお役立てください。


