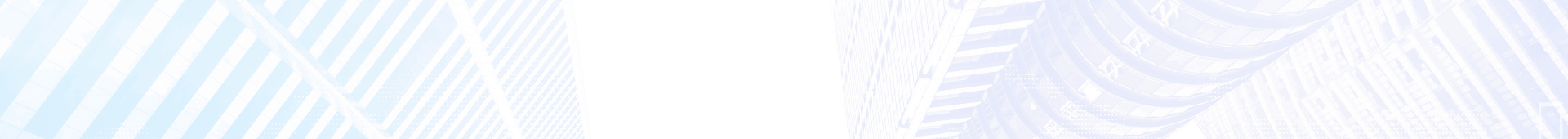

売れるプロダクトがあっても、それだけで成長は持続しません。属人的な営業は限界を迎え、プロセスの曖昧さが成長を阻みます。 本記事では、PMF後に必要な営業体制の最小構成と、役割分担・プロセス整備の実務的な考え方を解説します。
営業体制の整備は、PMF達成後が本格化のタイミングですが、PMF前にも「仮説検証型の営業活動」は必須です。とくに、初期顧客からのフィードバックを得るには、スクリプト化されていない泥臭い営業活動が欠かせません。
このフェーズでは、組織的な分業よりも、創業メンバーやプロダクト責任者が直接顧客と対話し、課題・導入障壁・意思決定構造などを定性情報として吸い上げることが重要です。
そのため、PMF前の営業は「効率」よりも「学びの多さ」を重視し、プロダクト改善や市場理解に活かすことを目的としましょう。
PMFを達成したSaaS企業が次に直面するのは、「営業のスケール」の壁です。
多くは属人的な営業スタイルから抜け出せず、再現性のないまま売上が頭打ちになります。つまり、プロセスが担当者の経験や勘に依存し、共有可能な基準がないという営業課題です。
この段階で必要なのは、役割とプロセスを構造化し、属人性から脱却する営業体制の設計です。
営業が個人技で回らなくなったとき、次に必要なのは「役割分担」です。
ここでは、初期フェーズでも機能するミニマムな営業体制モデルとして、SDR・BDR・AE・プレイングマネージャーの4つのポジションを整理し、それぞれが担う役割を解説します。
SDR(Sales Development Representative)とは、マーケティング部門と連携し、流入リードへの初期接点を創出する役割です。電話・メール・フォームなどのチャネルを用いて顧客と接触し、ニーズを引き出しながら商談化の前段階まで進めるというミッションを担います。営業ファネルの上流を担うSDRは、接点の量と質が商談化率に直結するため、極めて重要なポジションです。
SDRには、対応スピード、的確なヒアリング力、情報整理・記録の正確性といったスキルが求められます。
BDR(Business Development Representative)とは、インバウンド以外のチャネルから新規顧客を開拓するアウトバウンド型の営業ポジションです。リスト作成やターゲティング、アプローチ文面の設計を通じて、自社と接点のない潜在層への接触を担います。ミッションは市場全体の機会損失を減らすことであり、競合や業界動向を踏まえたセグメント戦略が欠かせません。
時間をかけて成果を追うため、仮説検証を回しながら改善を継続する力、情報収集力、論理的な仮説設計力が求められます。
AE(Account Executive)とは、SDRやBDRが創出した商談を引き継ぎ、顧客の課題ヒアリングから提案、クロージングまでを一貫して担う営業職です。特にBtoBのSaaSでは、導入判断に複数の関係者が関与するため、顧客の事業背景や導入目的を深く理解する力が求められます。
フォーマット化された提案手法を活用しつつも、個別の状況に応じた柔軟な対応が不可欠であるため、論理的な提案構成力、ファシリテーション能力、関係構築力といった複合的なスキルが必要です。
プレイングマネージャーとは、実務を担いつつ営業チームを指揮する役割です。少人数体制ではマネジメント専任者を置きにくいため、プレイングマネージャーが現実的な選択肢となります。個人で営業を回しながら、ファネル設計・KPI管理・プロセス改善なども担当し、チーム全体の動き方を現場に落とし込みます。
数値と実態の両面を理解した上で意思決定を行えるため、立ち上げ期や過渡期の営業組織において、営業の再現性と柔軟性をつなぐ橋渡し役として重要な存在です。
立ち上げ期のSaaS企業は、広告やSEOなどインバウンド施策に偏りがちですが、一定の規模を超えると頭打ちになりやすく、中長期の商談創出にはアウトバウンドの併用が不可欠です。インバウンドは質とCPAに優れ、アウトバウンドはLTVの高い顧客を狙える特性があります。
営業戦略においては、フェーズや目的に応じて両施策の強みを活かし、「短期効率」と「長期的基盤構築」を両立するチャネル設計が求められます。
属人的な判断に依存すれば成果は安定せず、スケールができません。営業体制と並行して取り組むべきなのが、営業プロセスの標準化です。特にSaaSのような継続収益モデルでは、明確な役割と再現可能な手順の構築が不可欠です。
ここでは、PMF直後に最低限整備しておきたい6つのプロセス要素を紹介します。
PMF達成後のSaaS企業が直面するのが、属人的な営業から脱却するための「営業の仕組み化」です。鍵となるのは、役割分担とプロセス整備の両立。「誰が、何を、どう売るか」の設計が再現性を生みます。 まずは、SDRやAEなどのコアポジションを定義し、最小構成で回せる仕組みを整えます。リソース不足や検証スピードを重視する場合は、営業代行など外部支援の活用も有効です。 営業の仕組み化には手間と時間がかかり、限られたリソースで体制を整えるのは容易ではありません。 「やるべきことは見えたが動かせない」「属人化を脱したいが型がない」という状況では、外部パートナーの活用が有効です。仮説構築から検証、営業モデルの実装までを一貫支援する営業代行は、立ち上げ期の課題を前進させる強力な手段となります。
実働だけではなく、営業プロセスの設計と仕組み化にも強みを持つ企業を厳選。単なる人手の投入ではなく、課題の根本からアプローチできるパートナー選びにお役立てください。


